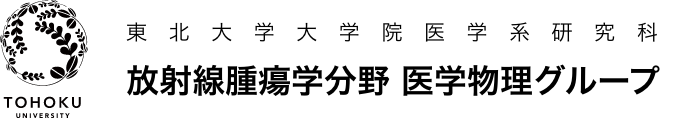2016年6月18日:CMPFG第42回定例会
首都大学東京荒川キャンパスで開催されたCMPFG第42回定例会に講師として助教角谷先生、博士課程3年の菅原さん、博士課程2年の勝田さん、博士課程1年の中島さんが発表され、修士課程2年の高山さんと宮坂さん、修士課程1年の阿部さん、家子さん、池田さん、昆さんが参加しました。
■日時: 2016年6月18日
■場所: 首都大学東京荒川キャンパス
■学会: MPFG第42回定例会
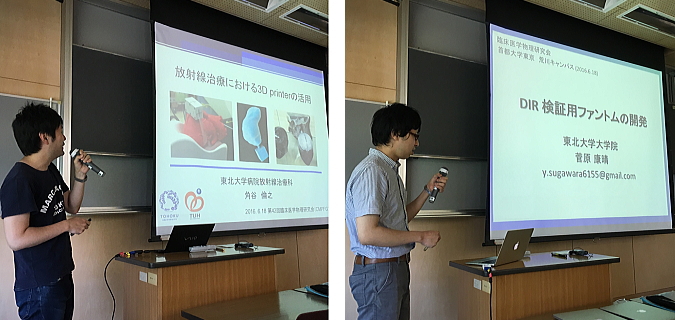
東北大学大学院放射線腫瘍学分野 一般コース
修士課程1年 阿部 幸太
2016年6月18日に首都大学東京荒川キャンパスで開催されたCMPFG第42回定例会(担当:東北大学)に助教角谷先生、博士課程3年菅原さん、博士課程2年勝田さん、博士課程1年中島さんが講師として参加、修士課程2年の高山さんと宮坂さん、修士課程1年の阿部、家子、池田、昆で参加して参りましたので報告させていただきます。
CMPFG第42回定例会ではテーマとして「State-of-the-art Radiotherapy」が掲げられ、日頃より医学物理会の発展に貢献されておられます5名の東北大学の先生方による講義形式のプレゼンテーションを拝聴致しました。参加者は首都大学東京・東北大学の大学院生や全国で活躍されている医学物理士の方々を含む48人でした。
午前中は、中島さんから「4D-CT ventilationの精度検証とVisual feedback systemの有効性の検討」について、勝田さんから「DVHに基づく患者QAに向けて」について、ランチョンセミナーでは担当がエレクタ株式会社様でmonaco5.1やcatalystについて、午後は菅原さんから「DIR検証用ファントムの開発」、角谷先生から「放射線治療における3D printerの活用」、放射線治療学分野の市地さんから「Markerless dynamic MLC trackingの技術開発」についてご講演いただきました。
近年、照射技術がほとんど確立されている中でより高精度な治療を行うために機能画像をDIRで作成し治療計画に取り入れることやDIRを用いて患者の積算線量を算出するなどDIRの技術が幅広く臨床応用され始めています。今回の定例会では、DIRにも不確実性がありそれを検証し、不確実性を理解したうえで運用することの重要性を再認識しました。そこで検証用のファントムを作成するために注目されているのが3D printerの技術であり、DIRによる変形精度の検証のみならず、線量の実測が可能なファントムの作成が期待されています。将来的には3D printerでのファントム加工が医学物理士の仕事になる可能性もあり、我々の研究室でもこの分野の研究に力を入れていくことが重要であると感じました。また、Markerless dynamic MLC trackingについて市地さんから技術の根本となる部分から講演していただきましたが、新たな手法を生み出すには、一つのモデルを考案し、改善点を発見し、その部分を改善したモデルを考案して、の繰り返しであることを再認識しましたので、今後の自分の研究に臨む姿勢の参考としていきたいです。また、この講演後の質疑応答では医学物理士の方々による臨床の経験をふまえた意見との討論が活発的であり、様々な現場の視点からの意見交換の場は今後も重要なものになると感じました。その後に行われた懇親会でも、他の施設や学校の方々から貴重なお話を聞くことができ、とても有意義な1日となりました。
最後になりましたが、貴重な勉強の場を提供してくださった主催の首都大学東京大学院人間健康科学研究科放射線科学域の方々、また臨床医学物理研究会の方々、エレクタ株式会社の方々にこの場をお借りして感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。