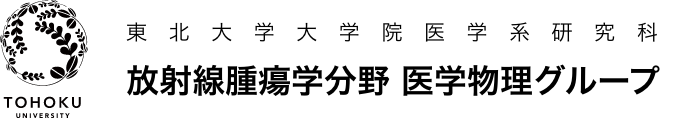2017年11月11日:CMPFG第48回定例会
首都大学東京荒川キャンパスで開催されたCMPFG第48回定例会に助教角谷先生、助手高山先生、博士3年の金井さん、博士2年の中島さん、博士1年の宮坂さん、修士2年の家子さん、修士1年の梶川さん、佐藤さん、松本さん、松田さんが参加しました。
■日時: 2017年11月11日
■場所: 首都大学東京荒川キャンパス
■学会: CMPFG第48回定例会

東北大学大学院医学系研究科 放射線腫瘍学分野 医学物理士コース
修士課程1年 松田 匠平
2017年11月11日に首都大学東京荒川キャンパスで開催されたCMPFG第48回定例会に、助教の角谷先生、助手の千葉先生、髙山先生、博士課程3年の金井さん、博士課程2年の中島さん、博士課程1年の宮坂さん、修士課程2年の阿部さん、家子さん、池田さん、昆さん、修士課程1年の梶川、佐藤、松本、松田で参加して参りましたので報告致します。
今回は「未来を切り開く放射線治療」をテーマに、国立がん研究センター中央病院と昭和大学の計4名の先生方からご講演をいただきました。午前の部は脇田先生から「深層学習」についてご講演いただき、近年話題のディープラーニングとはなにか?放射線治療にどう応用できるかという内容でした。ランチョンセミナーでは岡本先生から「MR-linac」についての講演をいただきました。本邦初のMR一体型放射線治療装置であるMRIdianの概要と、従来のCTベースのプランニングと比較して、照射中リアルタイムでの位置照合が可能であるという利点に衝撃を受けました。午後の部では、宮浦先生が「遠隔治療計画の支援」、中村先生が「BNCTの原理の臨床導入」について講演され、地域における医療格差の是正するために、病院間での情報共有とそのためのシステム構築が不可欠であることを知りました。またBNCT(Boron Neutron Capture Therapy:ホウ素中性子補足療法)については、臨床応用するにあたり線量特性の検証やヘッド内のモデリング等、課題が山積みであるとのことで現状手探り状態でのコミッショニングに難儀を示しておられました。
放射線治療技術が向上し、いかに高度な治療法を提供できるとしても、当然臨床導入するためには装置の線量測定やコミッショニングが欠かせず、それらの物理特性を自ら考えていかなければならないことを改めて認識したと同時に、今後物理士としてのトレーニングを積む上での糧としていきたいと考えております。
セミナー終了後、CMPFGは記念すべき10周年を迎えたということで、今回の意見交換会は浅草屋形船での実施となりました。そこでも各方面の先生方と交流させていただき、実臨床や研究に関する貴重な話を聞くことができました。
最後になりましたが、この度貴重な場をご提供してくださりました、国立がん研究センター中央病院と昭和大学の先生をはじめ、臨床医学物理研究会の皆様、首都大学東京大学院健康科学研究科放射線科学域の方々にこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

最近話題の深層学習

懇親会の様子

屋形船から眺めるスカイツリー