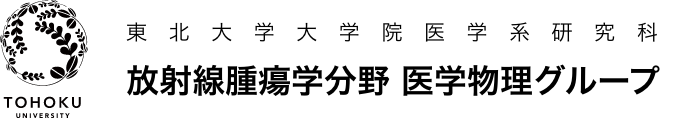2017年5月26~5月27日:日本放射線腫瘍学会小線源治療部会 第19回学術大会
奈良県文化会館で開催された日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第19回学術大会にて、修士課程2年の阿部さんが口頭発表してきました。
■日時: 2017年5月26日~5月27日
■場所: 奈良県文化会館
■学会: 日本放射線腫瘍学会小線源治療部会 第19回学術大会

東北大学大学院医学系研究科 放射線腫瘍学分野 一般コース
修士課程2年 阿部 幸太
2017年5月26日~27日に奈良県文化会館(奈良県奈良市)で開催された日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第19回学術大会にて、修士課程2年の阿部が口頭発表して参りましたので報告いたします。
近年、画像誘導小線源治療(IGBT)が発展、普及しつつあり治療計画が2次元から3次元に移行し始めております。しかし、3次元治療計画への移行はまだ完全ではなく、施設間の差はまだまだ大きいものがありますので、標準化やガイドラインの普及が大きな課題となっています。この様な背景から今回の学会は「IGBTの発展と標準化、個別化」というテーマで行われました。
本学会の2日目には「小線源治療における不確かさ」に関するシンポジウムが設けられました。シンポジウムでは医師、物理士の著名な先生方が小線源治療特有の不確かさに関する口演をされており、自分自身も興味がある内容でしたので大変参考になる口演でした。不確かさ評価をするということは自分が行うプロセスを総合的な観点から見ることができているということになるため、臨床現場と研究の両面で重要となるものだと再認識いたしました。
さて、私は、3次元治療計画に移行し始めてから、小線源治療用計画装置にも実装され始めている不均質補正線量計算アルゴリズム(Model-based dose Calculation algorithms)の計算精度に関する研究を行い、その成果を発表いたしました。現在小線源治療時の線量計算としては、体内を全て水と仮定するTG43法が主流となっています。しかし、不均質補正線量計算を用いて小線源治療時の線量計算の精度が向上されることで、DIRを用いた線量合算の高精度化にも繋がる可能性があります。小線源部門で不均質補正線量計算の報告はまだ少ない状況であり、DIRの線量合算と合わせて検討している例はさらに少ない状況ですので我々の研究室で不均質線量計算とDIRを用いた線量合算の研究を継続して行い、今後も様々な学会等で発表できればと思います。
最後に、今回の学会で得た知識を自分の研究、臨床現場に活かしていきたいと考えております。このような機会を与えてくださった皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。

せんとくんが出迎えてくれました

学会の様子

学会の合間に東大寺を観光しました。