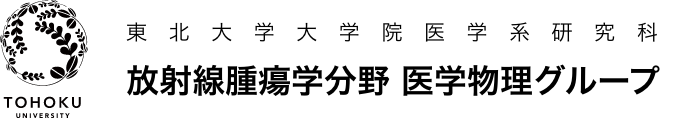2018年6月3日~6月8日:WC 2018
3年に1度開かれる医学物理分野最大規模の国際会議であるWC2018 (IUPESM World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering 2018) がプラハ(チェコ)で開催され、修士過程2年の松田さん、松本さんが口頭発表、博士課程3年の中島さんがポスター発表をしました。
■日時: 2018年6月3日~6月8日
■場所: Prague Congress Centre, Prague, Czech Republic
■学会: IUPESM World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering 2018

東北大学大学院医学系研究科 放射線腫瘍学分野 医学物理士養成コース
修士課程2年 松本 拓也
2018年6月3日~8日にかけてチェコのプラハで開催されたWC2018 (IUPESM World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 )に、博士課程3年の中島さん、修士課程2年の松田、松本が参加しましたのでご報告致します。
WCはIUPESM (International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine) が主催する医学物理学及び生物工学の国際会議で、3年に一度開催されます。開かれる都市は開催毎に異なり、今回はプラハで開催されました。プラハは中世の街並みが今も残り、世界で最も美しい街の一つともいわれています。旧市街の丘の上に位置するプラハ城は「世界で最も古く大きい城」と言われ、その大きさに圧倒されました。
私は新たな患者線量検証法として注目されている三次元体内線量再構成法の二つの異なる法を比較し、「Quantifying the performance of two different types of 3D patient dose reconstruction: machine log-file vs. machine log-file with EPID image」という演題名で口頭発表をしました。各線量再構成法の原理を把握し特徴を正しく理解することは、臨床で行う患者線量検証の結果を解釈・判断するうえで非常に重要です。今回の検証では各システムの性能を定量的に比較・解析を行いました。
今回の国際会議では英語での口頭発表を初めて経験し、質疑応答などの他の研究者との議論も全て英語で行いました。その中で、自分の研究を海外の研究者により理解してもらうためにも英語の訓練は必須であると実感しました。
3年に一度の開催ということもあり、非常に多彩な発表内容がみられました。近年注目を浴びている人工知能 (AI) やRadiomicsをはじめ、当研究室のテーマでもあるDIRやPatient QAについての発表も多数あり、非常に勉強になりました。この国際会議で得られた経験を今後の研究に活かしていきたいと考えております。
最後になりましたが、発表を行うにあたり熱心に指導をして下さいました先生方、海外発表という貴重な機会を与えてくださいました放射線科医局の先生方に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
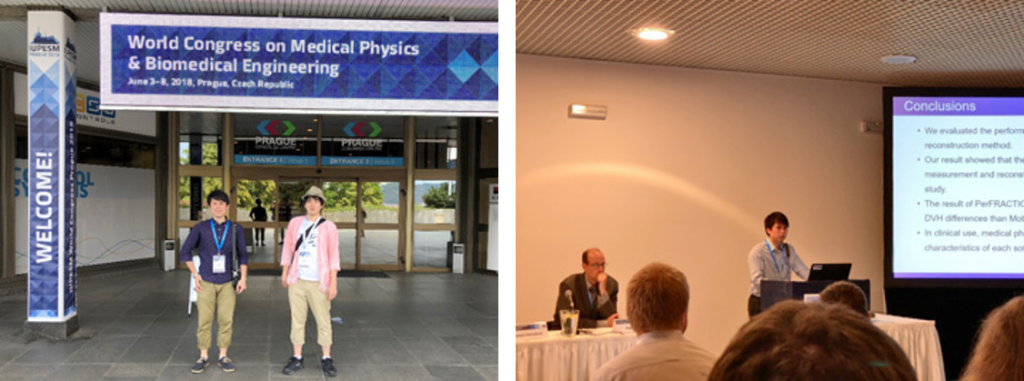
左:会場前での集合写真 右:発表の様子

プラハの街並み